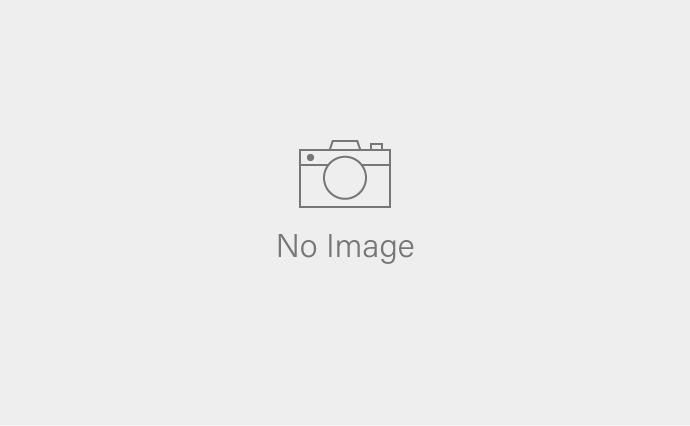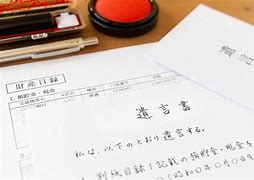(1)自筆証書遺言(民法第968条)
自筆証書遺言とは遺言者が自分で全文を手書きして作成する遺言書です。
◆主な特徴
・作成方法 : 全文・日付・氏名を自筆し、押印が必要、用紙、縦書き・横書きは自由
・費用 : 基本的に無料(法務局保管制度利用時は手数料あり)
・証人 : 不要
・保管 : 自宅など自由に保管可能、法務局での保管制度もあり
・検認 : 相続発生後に検認手続きが必要(法務局保管制度を利用すれば不要)
・リスク : 紛失・改ざんの恐れ、法的要件を満たさないと無効になる可能性が高い
◆ポイント
・財産目録はパソコン作成可(署名・押印が必要)
・法務局保管制度を使えば、検認不要・改ざんリスク低減
◆メリット
・費用がほとんどかからないので手軽に書ける
・遺言を作成したこと及びその内容を他の人に知られないようにできる
◆デメリット
・遺言の実現が不確実
・家庭裁判所に検認の申立てが必要
・検認しないで遺言を執行すると、5万円以下の過料に処せられる
・遺言の方式に不備があると無効になる可能性がある
(2)公正証書遺言(民法第969条)
公証人が遺言者の口述をもとに作成する公文書形式の遺言書です。
◆主な特徴
・作成方法 : 遺言者が口述→公証人が文書化
・費用 : 公証人手数料は必要(財産額に応じて変動)
・証人 : 2名の立会いが必要
・保管 : 原本は公証役場で保管、正本・謄本は遺言者が保管
・検認 : 不要
・リスク : 費用がかかる、証人が必要なため内容の秘密保持が難しい場合も
◆ポイント
・字が書けない方でも作成可能(公証人が代筆・代署)
・公証人に出張してもらうことも可能、病室等での作成も可能
・相続トラブル防止に有効、信頼性・安全性が高い
◆メリット
・公証人があらかじめ方式や内容の実現可能性を確認するため、確実に遺言を残すことができる
・公証人が遺言者の遺言能力の有無を確認するので、後ほど争いになる可能性が低い
・家庭裁判所の検認が不要なため、相続発生後すぐに遺言の執行が出来る
・原本は公証役場に保管され万が一正本や謄本を紛失しても再発行ができ、改ざん・紛失の恐れもない
・故人が公正証書遺言を残していた場合、相続人等は公証役場に遺言が保管されているか照会できる
◆デメリット
・公証人手数料がかかる
・作成時のコストがかかるので、気軽に内容の変更ができない