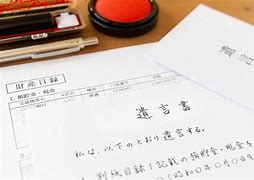(1)相続人が複数いる場合
・ 子どもが複数いる、兄弟姉妹がいるなど、法定相続人が複数いると、遺産分割で揉める可能性があります。
・ 特定の人に多く遺したい場合(例:介護してくれた子どもに多く渡したい)も、遺言書が必要です。
(2)相続人以外に財産を渡したい場合
・ 内縁の配偶者、事実婚のパートナー、友人、団体など、法定相続人でない人に財産を渡すには遺言書が不可 欠です。
(3)子どもがいない場合
・ 配偶者がいても、子どもがいない場合は兄弟姉妹やその子(甥・姪)が法定相続人になることがあります。
・ 兄弟姉妹との関係が希薄な場合でも、遺言がないと法定相続分が発生します。
(4)配偶者にすべての財産を渡したい場合
・ 遺言がないと、配偶者と兄弟姉妹で分割される可能性があります。
・ 遺言書で「すべて配偶者に相続させる」と明記すれば、希望通りの分配が可能です。
(5)内縁関係や事実婚の場合
・ 法的な婚姻関係がないと、配偶者としての相続権はありません。
・ 遺言書がないと、まったく財産を受け取れない可能性があります。
(6)相続人がいない場合(単身者など)
・ 相続人がいないと、財産は最終的に国庫に帰属します。
・ 遺言書があれば、信頼できる人や団体に財産を託すことができます。
(7)事業を営んでいる場合
・ 会社や店舗などを誰に継がせるかを明確にしておかないと、事業継続が困難になることがあります。
・ 特に家族経営や個人事業主の場合は、事業承継の意思表示が重要です。
(8)不動産を所有している場合
・ 不動産は分割が難しく、相続人間でトラブルになりやすいため、誰にどの物件を渡すかを明記しておくと安心です。
(9)再婚・前婚の子どもがいる場合
・ 前妻・前夫との子どもと現配偶者の間で相続トラブルが起きやすいため、遺言書で配分を明確にすることが重要です。
(10)相続税対策をしたい場合
・ 遺言書によって財産の分け方を工夫することで、相続税の負担を軽減できる場合があります。
(11)ペットの世話を託したい場合
・ ペットの飼育費や世話をしてくれる人への財産分与を記載することで、安心して託すことができます。