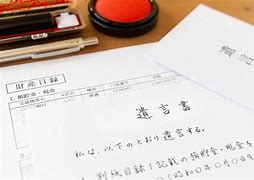相続人の範囲の原則は、民法により「配偶者は常に相続人」とされ、その他の相続人は順位に従って決まります。
配偶者(法律上の婚姻関係)は常に相続人になります。ただし、内縁関係の配偶者は相続人には含まれません。
第1順位は被相続人の子(直系卑属)が相続人になり、子がすでに死亡している場合は、その子(孫)が
代襲相続人となります。養子も相続人に含まれます(普通養子・特別養子ともに)。
第1順位の相続人がいない場合に限り、第2順位として直系尊属(父母・祖父母)が相続人になります。
より近い世代(父母)が優先されます。
第1・第2順位の相続人がいない場合に限り、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が死亡している場合は、
その子(甥・姪)が代襲相続人になります。
(1)同時死亡の推定
複数の人が同じ事故や災害などで死亡した場合に、誰が先に亡くなったかが不明なときに、
法律上「同時に死亡した」とみなす制度です。これは主に相続関係を整理するために使われます。
(1-1) 背景と目的
・相続では「誰が先に亡くなったか」によって、遺産の分配先が変わることがあります。
・例えば、親子が同じ事故で亡くなった場合、親が先に亡くなったとされれば子が親の財産を相続し、
その後子の相続人に引き継がれます。
・しかし、死亡の前後が不明な場合に一方が他方を相続することは不合理になるため、民法では「
同時に死亡したと推定する」**と定めています。
(1-2) 民法の規定
・民法第32条の2
数人の者が死亡した場合において、その者のうちの一人が他の者よりも先に死亡したことが証明されない
ときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定します。
(1-3) 例
・交通事故や火災、自然災害などで家族が同時に亡くなった場合
・遺言がない場合の法定相続の整理
・保険金の受取人が被保険者と同時に死亡した場合の処理
(1-4) 補足:推定と認定の違い
・「推定」は法律上の仮定であり、反証があれば覆る可能性があります。
・医学的な証拠などで死亡時刻が判明すれば、「同時死亡の推定」は適用されません。
(2)二重の親子関係の成立
一人の子に対して、法律上の親子関係が複数存在する状態を指します。これは通常の親子関係とは異なり、
養子縁組などの制度が関係する特殊なケースで生じます。
(2-1) 二重の親子関係が成立する典型例
a.養子縁組による親子関係の追加
・実親との親子関係がある子が、他の人と養子縁組をすることで、実親+養親の両方と親子関係が
成立します。
・例:AさんがBさんとCさんの実子であるが、Dさんと養子縁組をした場合、AさんはB・C・Dの3人と
親子関係を持つ。
b.特別養子縁組の場合
・特別養子縁組では、実親との親子関係が終了し、養親とのみ親子関係が成立します。
・この場合は「二重」ではなく、親子関係が切り替わるため、二重の親子関係は成立しません。
(2-2) 民法上の根拠
・養子は養親の嫡出子とみなされます(民法727)。
・実親との親子関係は養子縁組によって消滅しない(特別養子縁組を除く)ため、通常の養子縁組では
二重の親子関係が成立します。
(2-3) 影響
・相続権の重複 : 養子は実親・養親の両方の相続人となる可能性があります。
・扶養義務の重複 : 養親・実親ともに扶養義務を負うことがあります。
・戸籍上の記載 : 養子縁組後も実親との親子関係は戸籍に残ります。
(2-4) 注意点
・二重の親子関係は法律上認められていますが、相続や扶養などの場面で複雑な判断が
必要になることがあります。
・特に遺言や相続対策を考える際には、親子関係の構造を明確にしておくことが重要です。
(3) 代襲原因
本来相続人となるべき人が、一定の理由で相続権を失った場合に、その人の子(または孫)が代わりに
相続人となる仕組みです。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と呼びます。
(3-1) 代襲相続が発生する原因(代襲原因)
・死亡
相続開始前に相続人が死亡している場合
・相続欠格
相続人が法律上の欠格事由に該当する場合(例:被相続人を殺害したなど)
・相続廃除
被相続人が家庭裁判所の審判で相続人を廃除した場合
・ただし、放棄(相続人が自ら相続を放棄した場合)は代襲原因にはなりません。
放棄した人の子は代襲相続できません。
(3-2) 代襲相続の対象となる相続人
・第一順位(子)が代襲される場合、その孫・ひ孫(再代襲)が代襲相続人になります。
・第二順位(親)や第三順位(兄弟姉妹)では、兄弟姉妹が死亡していた場合にその子(甥・姪)が
代襲相続人になります。
・兄弟姉妹の代襲は一代限り(甥・姪まで)です。再代襲は認められません。
(3-3) 注意点
・代襲相続人が未成年の場合、法定代理人の関与が必要になることがあります。
・相続関係説明図や戸籍調査で、代襲相続人の確定が複雑になるケースもあるため、慎重な確認が必要です。
・被代襲者が養子の場合、被相続人の子の子が代襲相続人となるためにはその子が被相続人の直系卑属で
なければなりません。
したがって、被相続人の子が養子でその養子に縁組前に出生した子がある場合には、その子は
養親との間に法定血族関係がなく直系卑属にあたらないため、代襲相続権が認められません。
(4) 再転相続
再転相続(さいてんそうぞく)とは、相続人が相続を受ける前に亡くなってしまった場合に、その相続人の
相続人が代わって相続することを指します。これは民法第991条に規定されている制度です。
(4-1) 再転相続の仕組み
・通常の相続:被相続人(亡くなった人)の財産は、法定相続人に引き継がれます。
・再転相続 :法定相続人が相続開始後に相続の承認・放棄をする前に亡くなった場合、
その人の相続人が「再転相続人」として、相続の承認・放棄をする権利を引き継ぎます。
(4-2) 具体例
1. Aさんが亡くなり、息子のBさんが相続人となる。
2. しかし、BさんはAさんの相続を承認・放棄する前に亡くなる。
3. Bさんの子であるCさんが、再転相続人としてAさんの相続について承認・放棄を選択できる。
(4-3) 再転相続の熟慮期間
再転相続人には、自己の相続開始を知った時から3か月以内に、承認または放棄をする必要があります
(熟慮期間)。これは、元の被相続人(Aさん)の死亡時ではなく、再転相続人自身が相続人となった
時点からカウントされます。
(5) 胎児の権利能力
相続人は相続開始時に生存していなければなりませんが、胎児については既に生まれたものとみなして
相続権を保障します(民法886①)。ただし、死産の場合には、初めから相続人にならなかったものと
します(民法886②)。通常、被相続人(=父)の死亡時に、妻(=母)が懐胎している場合は、妻が
出産して安定してから遺産分割をします。
(6) 相続人の欠格
被相続人が欠格者に遺贈をしていても受遺者になれません(民法891・965)。相続欠格は特定の相続人に
対する関係にのみ相続権が剥奪されるに止まり、別の相続との関係では相続資格があります。
欠格の効果は一身専属だから欠格者の子には影響しませんので子が代襲相続することができます。
(7) 相続人の廃除
相続人廃除の効果は相対的であり、被廃除者は当該相続についてのみ相続権を失います。廃除されても
受遺者としての地位に影響はありません(民法965)。廃除の効果は一身専属だから被廃除者の子には
影響しないので代襲相続が可能です。