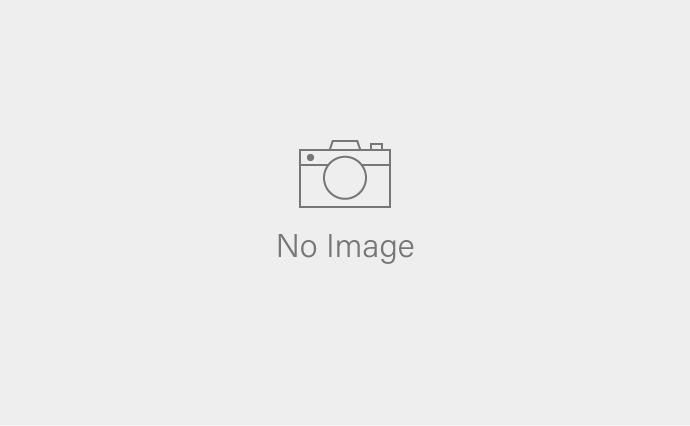1.宅地建物取引業法の主な目的
宅地建物取引業法 第1条(目的)
「この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。」
(1)公正な取引の確保
・不動産取引における情報の非対称性(売主と買主の知識差)を是正し、安心して取引できる環境を整える。
・虚偽の説明や不当な勧誘などを防止。
(2)消費者保護
・一般消費者が不利益を被らないよう、重要事項説明や契約内容の明確化を義務付けている。
・手付金の保全措置や契約解除のルールなども整備。
(3)業界の健全な発展
・宅建業者の登録制度や監督制度を通じて、信頼性の高い業者のみが活動できるようにする。
・不正行為への罰則や業務停止命令なども規定。
(4)社会的・経済的秩序の維持
・不動産は生活の基盤であり、投資対象でもあるため、取引の安定性は社会全体に影響を与える。
・地価の安定や都市計画との調和にも寄与。
2.宅建業(宅地建物取引業)とは
宅建業とは、宅地や建物の売買・交換・貸借に関する「代理」や「媒介」を、業として反復継続的に行うことを指します。これは、宅地建物取引業法第2条で定義されています。
(1)宅建業の構成要素(4つのキーワード)
・宅地―建物の敷地として使われる土地、または都市計画法上の用途地域内の土地
・建物―柱・壁・屋根のある構造物(住宅・店舗・事務所など)
・取引―売買・交換・貸借の「代理」または「媒介」行為(自己所有物件の単発売却は含まれない)
・業 ―不特定多数に対して、反復継続して行うこと(営利性がある)
(2)宅建業に該当する例
・不動産会社が顧客の土地売買を仲介する
・賃貸物件の紹介を継続的に行う
・建売住宅を分譲する事業者
これらはすべて「宅建業」に該当し、免許が必要です。
(3)宅建業に該当しない例
・自宅を一度だけ売却する
・自分の所有する建物を貸す(大家業)
・国や地方公共団体が行う不動産取引
これらは「業」としての反復性や不特定多数への取引がないため、宅建業には該当しません。